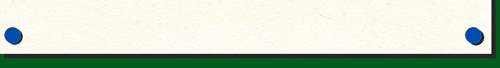パリ日本語補習校で行なわれたイベントや野外活動などについて、
保護者から寄せられた声をご紹介します。
更新:2024年2月10日
・第15回 音読発表会 保護者の感想
1月24日(水)、27日(土)に音読発表会を行いました。
各教室にて15分ずつ発表しました。
感想を保護者の方々よりいただきました。
今年度も音読発表会にて、子ども達の生き生きとした発表を見ることができ、とても感動いたしました。
私は子どもの通う3クラスの音読発表会を参観することができました。
小1下クラスは「おかゆのおなべ」。
少し緊張した様子のお子様達。そんな中でも号令や自己紹介、音読発表と皆さんそれぞれ一生懸命発声し、頑張っている様子が素晴らしかったです。昨年よりも長い文章が読めるようになり、とても成長を感じました。そろって読むところなどとても可愛かったです。
小2下クラスの発表は「お手紙」。
文中の悲しそうな時や励ましや嬉しい時の表現など、皆さん感情を込めて読んでおりとても素晴らしかったです。たくさんの保護者の皆様の前で緊張もしていたと思いますが、それぞれのご家庭での練習の成果も出ており、欠席のため急遽代役で読んでくれた生徒さんもとても上手に読めていて、生徒皆さんの頑張りが伝わってきました。
小4下クラスは「プラタナスの木」。
生徒皆さん発表する事にも慣れを感じ、安心して観ることができました。段々と学習する内容も難しくなってきましたが、それぞれ本の内容をきちんと理解し、強弱や気持ちを込めて読む、間を取りながら読んだりと皆さんとても素晴らしかったです。
ワイルド先生も仰られておりましたが、週に一度の補習校の授業と各ご家庭での学習の中でこんなにも読めるようになり、皆さんの頑張りに感動いたしました。
生徒の皆さん、ご指導いただいております先生方、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
小1下、小2下、小4下クラス保護者 菊池恵
今年も綿密なスケジュールの元、先生並びに保護者の皆様とのご協力により、音読発表会を無事執り行うことができました。先生方におかれましては、通常の授業に加えて本イべントに向けてご尽力をいただき誠にありがとうございました。
今回も授業参観形式でクラス毎の発表となりました。学校施設、クラスでの雰囲気や先生とのコミュニケーションを直接で感じることができる特別な機会となりました。
さて、我が家は現在小4下と小3下クラスに通っております。二人とも、「あかるい あさひだ あいうえお」の新小1上からスタートし、早いもので上の子は今年で補習校8年目、下の子は6年目となります。
小3下の音読発表会は、ここで転んだら三年きりしか生きられないと伝えられているとうげを題材にした、民話の「三年とうげ」を読みました。うっかり転んでしまったおじいさんが絶望的になって寝込んでしまい、まるで一休さんのとんちを彷彿とさせる、ある少年の機転のきいた一言で最後には救われるという楽しいお話です。悲しくなったおじいさん、最後は嬉しくてしょうがないおじいさんの様子を上手に情感を込めて読んでくれました。自然の描写も落ち着いて読み、子供たちの大きな成長を感じる機会となりました。保護者の前で、はにかんだような何ともかわいらしい子供たちの表情が心に焼き付いています。先生と生徒間の強い信頼関係がよく伝わって来ました。
小4下は椎名誠の「プラタナスの木」を音読しました。文章は、特に話し口調のような部分では、意味が分かっていないと区切って読む事が難しい印象を受けました。これは流石、4年下の教科書だなと感じました。会がはじまると、雑音一つなくシーンと静まり返る中、子供たちは皆それぞれ、淡々と、絶妙なペースで、かつ非常に落ち着いて読んでいるではありませんか。感動の一言に尽きます。先生のご指導の賜物です。感謝申し上げます。
音読発表会を通じて、子供たちの日本語の上達と心の成長を垣間見ることができる貴重な体験となりました。子供たちにとっても人前で発表することは、これからの人生で大きな財産となる事と信じます。先生が仰ったように、毎週少しの時間でも、塵も積もれば山となります。この一瞬一瞬の時間を、信頼できる素晴らしい先生方と共に、パリの補習校で勉強できる環境がある事に感謝でいっぱいの気持ちです。
日頃よりご指導いただいている先生方、いつも生徒たちへの眼差しがやさしい校長先生、補習校運営にご尽力いただいている学校関係者すべての皆様へこの場を借りて深くお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
小4下 保護者代表 石﨑美奈子
更新:2023年2月10日
・第14回 音読発表会 保護者の感想
1月25日(水)、28日(土)に音読発表会を行いました。
各教室にて授業参観形式で15分ずつ発表しました。
感想を保護者の方々よりいただきました。
昨年と同様、各クラスの参観をずらした音読発表会。
細かく時間配分された時間に合わせて保護者一同、クラスに入室すると緊張した面持ちの子供たちがきれいに整列していました。
号令できちんと『気をつけ・礼』をして、一人ずつ名前の自己紹介。
緊張のせいかみんなとても早口!お父さんお母さんの拍手も追いつきません。
小二上クラスは、教科書の『ふきのとう』と『スイミー』を読んでくれました。 何週間も前から練習しているのを知っているのに息子が読むたびドキドキ。 クラスのお友だちの子も言いづらい箇所がある、など聞いていたけど、おうちや先生と一緒に何度も練習したのでしょう。 みんなとても上手に読め、誇らしげな顔、はにかんでいる顔が印象的でした。 初めは緊張している感じがありましたが、自信を持って読んでいる様子や周囲に配慮する様子など、 昨年に比べてひと回り成長した子どもたちを見受けられました。
現地校でもこのようなクラス参観がないので、家庭の中とはまた違う様子が見られるとてもありがたい機会でした。 普段から指導していただいている先生方、運営に関わっている方々がきめ細かく段取りを組んで下さったおかげで、 短時間ながらも子どもたちにとっても、保護者にとっても有意義な時間が過ごせました。ありがとうございました。
小二上クラス代表、土田
今年度も無事に音読発表会が開催され、先生方におかれましては常日頃のご指導に深謝申し上げます。 そして子ども達の成長した姿を見ることができました。
私は子供が4人おり、それぞれ新一年生クラス、小2上クラス、小4上クラスに2名受講している為、3クラスを参観することができました。
新一年生クラスの発表会では、「おおきなかぶ」と「あいうえおであそぼう」を読みました。
皆さん新一年生とは思えないくらいしっかりと読めていて驚きました。
日頃の練習の成果がよく出ていて、一生懸命な姿にとても感動いたしました。
娘の9月のスタート時には文章を平仮名一文字ずつ読んでいたので、その頃から考えると、
5ヶ月という短期間での成長に驚きと共に感激いたしました。
小2上クラスの発表会では、「ふきのとう」と「スイミー」を読みました。 強弱を着けたり、読み方を工夫したりと、皆さん感情を込めて読めていて素晴らしかったです。 前年度息子は少し早口で棒読みになっていたので、日頃の音読練習では、 物語を理解し一言ずつゆっくり感情を込めて読むことを練習していました。 今年度は息子も大分上達して読めていたのでこれからも頑張ってもらえたらと思います。
小4上クラスの発表会では、「一つの花」を読みました。 戦時中のお話で、自分達が経験した事がないことや悲しい場面もしっかり読めるようになっていてとても成長を感じました。 そして皆さん物語をきちんと理解し、一言一言に感情を込めて音読できていて本当に素晴らしかったです。
皆さんとても上手でとても感動いたしました。本当に素晴らしかったです。 また飯田校長から励ましのお言葉をいただき、皆さんしっかりと聞いておりました。 これからも引き続き日本語を楽しく学んでいってもらえたらなと思います。 先生方には心より感謝とお礼を申し上げます。 そして今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
新一年、小2上、小4上クラス保護者 菊池恵
更新:2022年2月21日
・第13回 音読発表会 保護者の感想
1月26日(水)、29日(土)に音読発表会を行いました。
今年は、各教室にて授業参観形式で15分ずつ発表しました。
感想を保護者の方々よりいただきました。
年明けからオミクロン株が猛威を振るいだし、フランスの新型コロナウィルス感染者数が50万人という数を突破してしまった中、無事開催された音読発表会。
我が家にとってはパリ日本語補習校に新一年生として昨年入学してから初めての行事となりました。
会場の各教室がある4階に上がると先生方が作ってくださった「音読発表会」と掲げられたパネルが目に入り、親である私も少しワクワク、且つ懐かしいような気持ちに。
まずは皆で礼をし、自己紹介をして開始となりました。
フランスに住み家庭内で日本語で過ごしていても「礼」を見ることもすることもほぼありませんので、改めて補習校で少しでもこのような機会を作ってくださることの大切さを実感しました。
「おおきなかぶ」の発表へ移ります。
担任の先生がマスク着用をして読んでも苦しくならないよう、一人一人が順々に読む文をあまり長くならないように、とご配慮下さいました。
挨拶の場面から始まり最後まで息子にはハラハラさせられましたが「うんとこしょ、どっこいしょ」など音読は無事でき、ホッと胸を撫でおろしました。
クラスのお友達も皆自分の担当箇所をがんばって読んでいました。
コロナ禍の大変な状況の中、今回の音読発表会開催に向け様々な面で準備に尽力してくださった先生方に感謝申し上げます。
来年の音読発表会がどのようなものになるか、これからの皆さんの成長が楽しみです。
新1年保護者 名取 あゆ子
今年は、授業参観形式のクラスごとの音読発表会でした。
子どもたちが授業を受けているクラスを初めて訪れ、新1年と小1下の発表を参観しました。
普段はしない、礼と挨拶も上手にできていました。
新1年は「おおきなかぶ」と「あいうえおであそぼう」、1年下は「ずうっとずっと大すきだよ」と「日づけとよう日」の発表でした。
一人ずつ読む箇所と、みんなで一緒に読む箇所があり、マスク越しでも生徒さんの頑張りが伝わってきて、大変楽しく見させて頂きました。
この一年間の成長を直に見る貴重な機会を、ありがとうございました。
コロナウィルスの流行が続くなか、音読発表会を開催頂いた補習校の先生方に感謝申し上げます。
新1年、小1下クラス保護者 鶴 真紀子
更新:2021年4月5日
・オンライン音読発表会 保護者の感想

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、
今年の音読発表会は各クラスでオンラインによる発表となりました。
その感想を保護者代表の方よりいただきました。
今年の補習校の音読発表会は、コロナウイルス流行の影響でクラスごとのオンラインでの発表会となりました。
中学クラスの音読作品は、夏目漱石の『坊ちゃん』の冒頭部分です。
普段の会話や現在の社会では使われない単語や言い回しが多いにも関わらず、皆堂々とした発表でした。
しかも強弱や抑揚を考えて読んでいるということで、理解したうえでの発表だとわかります。
一部分とはいえ明治の文豪の作品を読めているということに感動いたしましたし、子供たちの成長を頼もしく、また誇らしく感じました。
ここまでご指導くださった先生方のご尽力に感謝の思いでいっぱいです。
困難な状況の中、音読発表会を開いてくださった補習校の先生方には心よりお礼を申し上げます。
生徒のみなさん、お疲れさまでした。これからも日本語の勉強を頑張ってください。
中学クラス保護者 高橋潤子
沢山の人々の前に立って音読を発表する子供たち、ドキドキしているんだろうなぁ、と思いながら毎年音読発表会を観賞しています。
今年はクラスごとのオンライン発表会。小さな会場にぎゅうぎゅう詰めになって自分達を見つめる大人の顔はなくても、
カメラに向かっての発表もそれなりに緊張感があったと思います。
私が観賞させていただいた小3下のクラスは授業で各々が書いた物語を発表。
小5クラスは音読の後、自分を紹介するスピーチ。どちらも例年の音読発表会とは違い、各生徒さんの個性が現れてとても楽しく観賞させていただきました。
クラス単位というのも授業参観の様で良いものだなあと思いました。
黄色いベスト運動に続いてコロナウイルス流行と補習校の運営への影響が続いている中、
先生方には最善の努力、対応をいただき心より感謝致しております。この場をお借りして深くお礼を申し上げます。
小3下、小5クラス保護者 デュランディ恵子
更新:2017年11月5日
秋の遠足 栗拾いご報告
10月8日に行なわれた栗拾いのご報告を
小1下クラス代表の保護者の方よりいただきました。
栗拾い
秋の味覚狩り、栗拾いへ、さあ!!
重たい曇り空を吹き飛ばす勢いで向かったムドンの森。
家族連れ70名ほどで森に入り、
スタートの合図でパーッと散り散りに。
湿った落ち葉を踏みしめ、奥に進めば進むほど、
落ちてる、落ちてる!
いがをちょっと剥くとピカピカの栗が顔をのぞかせ、
面白いようにとれるのです。
時間を忘れて子どもも大人も大はしゃぎ。
栗拾い後のお楽しみ、ピクニック+レクリエーションも賑やかに。
食べ続ける人、森に入って自然観察する人、
栗笛作りに熱中する人、ドッヂボールや長縄飛び、
サッカーで汗を流す人、etc.…。
いい空気を吸って、楽しく笑い、体を動かし、
素敵な秋の1日を皆さんと共有しました。
「在校生・保護者のみなさんへ」のページに、校長先生のコラム
「栗拾い雑感」と、栗拾いの写真を掲載しています。
写真は「校長先生のフォトギャラリー」からご覧になれます。
*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2015年11月5日
秋の遠足 栗拾いご報告
10月11日に行なわれた栗拾いのご報告を
六藤佳世子様よりいただきました。
栗拾い
10月11日の日曜日に、総勢70名で栗拾いをしました。
車組は直接、栗拾いをする駐車場へ、電車組は、RER-C線の Chaville-Velizyで待ち合わせをして、恒例の「お手洗い」。 森にはトイレがないので、まずはみんなでカフェのトイレに行きます。今ではこれが恒例になってしまいました。 そこから子供たちも楽しみにしている、栗拾いの場所、車組と合流します。
子供も大人も、いっぱいの栗を拾いました。 中には、数を数えてる人、いっぱい拾った栗を、得意げに見せてくれる子供や大人の方もいました。 私は心の中で、栗の皮むき、「Bon courage!」と思わず呟いてしまいました。
栗拾いでおなかがすいた後は、場所を移動し、みんなでピクニック。
お日様が気持ちよく、おなかがいっぱいになった後は、お昼寝でもしたくなるようなお天気でした。
でもお昼寝なんかしてる暇なんかありません。
栗拾いといえば、校長先生も参加のドッジボール。
まずは、ドッジボールをするためのラインをテープで引きます。
用意できれば、さあ開始!
男の子と女の子に分かれて、試合が始まりました。
お父さんやお母さんも加わります。
中には歓喜を上げる子供たち。
ぎゃーぎゃーわいわい、ボールをよけて、右や左に逃げる子供たち。
勝ち負けなんか関係ありません。
あっ--、ドッジボール楽しかった!!
これで、そろそろ栗拾いもお開きです。
「みなさん、お疲れさまでした。本当にいい1日でしたね。」 今でも、子供たちの楽しそうな声が聞こえてきそうです。
六藤佳世子(土曜 小5、6年クラス)
栗拾いの写真を「在校生・保護者のみなさんへ」ページの「校長先生のフォトギャラリー」に掲載しています。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2015年7月5日
運動会ご報告
6月7日に行なわれた「運動会」のご報告を
BONVIN まりこ様よりいただきました。
参加者みんなで作る運動会
6月7日日曜日、AFFJ(日仏家族の会)主催の運動会に、私たち家族は初めて参加しました。日本語補習校からは、44名の参加があり、総勢130名とのことでした。
当日は、真っ青な申し分のない運動会日和。会場は、Issy-les-MoulineauxにあるParc de l'Ile de saint-Germainで、在仏12年目にして初めて足を踏み入れたのですが、大きな広場が二つ、子供の遊技場・乗馬クラブ・遊具を備えた施設や軽食店もある、緑あふれる素敵な公園でした。
会場についてすぐ、主体者意識の高い子供たちを たくさん!見つけました。
生まれや育ちはフランス!という子供たち。フランス人お父さんに至っては 学校で見たことも教わったこともない!練習なし!のぶっつけ本番の運動会です。 でも、自然と組ごとに所属感や連帯感が生まれて みんな、主体的に準備や競技にどんどん参加していました。
私が 印象にのこった競技は、 後半の花形ともいえる六組対抗リレ−です。 息子の組もきっと仲間で作戦を立て、 一生懸命走る順番を考えたと思います。 第一走者は、CPと思われる男の子がスタ−トラインに立っていました。
私が見渡す限りでは、一番小さくて 隣は中学生の大きなお姉さん。 彼の身長はお姉さんの腰くらい。 私は、「作戦ミスをしたかなぁ」
など、ふと、不謹慎な考えをしました。 そして、その子の顔を眺めて驚きました。 彼は真剣な顔で、責任感を持って、スタ−トの笛が鳴るのを待っていることが、はっきりと分かりました。 偉い!と思いました。 そして、笛が鳴ると、自分の持てる力を出して、大きい子供たちに負けずに、一生懸命に走って行きました。
「えらい!頑張れ!」声が出ました。 第三走者の息子へとバトンが渡され、3人のごぼう抜き、大声をあげて息子を応援しました。 子供たちは練習など一度もしていないのに、自分たちの仲間を確実に見つけ、バトンを渡していきます。 本当に凄い!と思いました。
そして最終アンカ−へとバトンが渡されると、場内は、子供たちや親たちにも熱が入り、 大きな声で応援合戦が繰り広げられました。
一生懸命に走り終えたあと、「一位じゃなかった。」
と、みんなは悔しがって戻ってきました。 私は、「みんなカッコ良かったよ! 頑張って走ってるって、おばさんは分かったよ。」と声をかけると、うんうんと頷くように、首を縦に振る子供たちの顔が、嬉しそうに 晴れ晴れとしていて、本当に印象的でした。
自分の思うようにならない体験、それを自由に子供たちに与えることができるAFFJ運動会の環境は、 私には初めての経験でしたが 素晴らしいなぁと思いました。 意欲を育てるって、こういうことなのかなぁ・・・とも。
閉会したのは16時半過ぎ。 最後に参加賞のメダルとプレゼントをもらい、競技で使用した風船を分けてもらって 嬉しそうにしている息子と仲間たち。 子供が成長する経過を 温かく見守ることができた、みんなで作る 楽しい・楽しむ運動会でした。
土曜日 小3上 廣重先生クラス 保護者代表
BONVIN まりこ
運動会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
更新:2015年5月5日
かるた会ご報告
4月11日に行なわれた「かるた会」のご報告を
ペ そんおぎ様よりいただきました。
かるた会
4月11日、毎年恒例のかるた大会が Saint Francois 校で行なわれました。
広々とした会場の所々に敷物が敷かれ、その上に様々なかるたが置かれ各自グループになりかるたを楽しめます。
先生や責任者の方等の決め事で進むのではなく、どの子も好きな輪に入り、好きなように参加できるスタイルがとても魅力的でした。
もちろんかるたを読むのも自由なので、読みたい子が率先して読む事ができます。
また、小学生はもちろんのこと、中学生以上の子も楽しんでいる様子が印象的でした。
様々なかるた、そして百人一首もありますので、小さな子から大きな子までが楽しめました。
その他おりがみコーナーもあり、おりがみと共におりがみの本、折り方プリントまで用意されていたので、子ども達はおりがみで作りたい物を探し、説明を見ながら自分のペースで好きなように作っていけます。
保護者の方も一緒におりがみをされ、子ども達が手こずっている箇所は一緒に折り方を探したりと非常に和気あいあいとした雰囲気でした。
一通り遊んだ後は、保護者の方々が持ち寄ってくださったおやつやお料理、飲み物などをみなでビュッフェ形式でいただきます。 どれも美味しく、そしてみなで一緒にいただく物ですので、ほっこりとした幸せな気分になりました。
異国にいながら、日本の文化・空気を一緒に共有できる貴重な空間でした。 普段、補習校で子ども達はそれぞれ顔は合わせてもお互い授業を受けるのみで、一緒に自由におしゃべりしたり遊んだりする時間は持てませんので、かるた大会を通じてたくさん遊べてより一層仲良くなり、この上ない良い機会でした。 校長先生、各担任の先生方も同席されゆっくりお話もできましたし、保護者の方々との交流もでき良かったです。
私個人の感想になりますが、普段引っ込み思案の娘(8才)が、折り紙で作った折り鶴を校長先生へプレゼントしていた姿を見て心が温かくなりました。 学校に関わるたくさんの方々が参加され、子ども達がそこでワイワイ楽しむ…とてもほがらかで幸せな、そしてこれからも続いていけたらいいなと思えるとても素敵な行事でした。 先生方、保護者の方々、ありがとうございました。
ペ そんおぎ(水曜日ワイルド先生小2上・下クラス)
かるた会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
更新:2015年2月11日
音読発表会ご報告
1月24日に行なわれた音読発表会のご報告を
新一年生クラスのお子さんのお母様よりいただきました。
仲間とともに「国語」を学ぼう
〜2015年 音読発表会に参加して〜
昨年9月に補習校の新一年クラスに入り、今年が初めての音読発表会でした。
後半の部は娘のクラスから発表が始まり(低学年から高学年の順というのがプログラムの通常だとは思いますが、初参加で何もわからない新一年生から発表・・というのはちょっとかわいそうな気が??)、緊張した新一年生の、小さな声を振り絞っての懸命な「おむすびころりん」が終了。4分あまりの発表でしたが、頑張ったみんなにお疲れ様、指導してくださった先生には感謝の気持ちを込めて拍手をしました。
そしてそれからは、保護者としてではなく、発表会の一観客としての感動を受けました。どの学年もすばらしく、今でもプログラムの演目を見ると生徒たちの音読が思い返されます。全体を通して感じたのは「国語の教科書は世代に渡って受け継がれるものだ」ということです。「スイミー」を聞きながら、小学校の学芸会で演じたな…と思い出し、「百人一首」を聞けば、友達と一緒に覚えた!…と懐かしくなり、「落語・時そば」は…残念ながら私の教科書には載っていた記憶がないのですが、さすが教科書、日本文化を網羅している〜と感心しました。一所懸命に練習した生徒たちの言葉だからこそ伝わってくるものがあり、国語の教科書だからこそ共感できる何かがありました。
フランスに住んでからは娘に「日本語」を習得させるのに必死で、アニメのDVDを見させたり、時にはパソコンでゲームをさせたり。それはそれで日本語力を身につけるのにはよい方法かもしれませんが、日本で日本の子どもたちが学んでいる「国語」を目標にするのなら、①学校で、②仲間とともに教科書を開いて、③先生に教えてもらう…これに勝るものはないでしょう。これから苦労することがでてきても、どうか頑張ってこの国語の教科書だけは読み続けてほしい、と強く思いました。
娘も上級生の発表を聞いて夢をいただいたようです。生徒の皆さんどうもありがとう!そして、準備をしてくださった先生方、保護者代表の方々(お茶会では本番を終えた子どもたちがほっと一息。保護者も交流できるよい機会でした)にもこの場でお礼を申し上げます。ありがとうございました。
来年は一回り成長した生徒たちからまた新しい発表が聞けるのですね。そしてあと7,8年もしたら娘の口から落語の台詞が聞けるのかも?!今から楽しみです。
K.Y.(新一年水曜クラス)
音読発表会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
また「在校生・保護者のみなさんへ」ページの「校長先生のフォトギャラリー」にも掲載しています。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2014年11月10日
秋の遠足 栗拾いご報告
10月12日に行なわれた栗拾いのご報告を
田草川(たそがわ)俊美様よりいただきました。
栗拾いとドッジボール
テルテル坊主、明日天気にしておくれ…息子達が作った甲斐あったのか雨が止み、10月12日、待ちに待ったムドンの森の栗拾いに家族で参加しました。
今年は50人以上の参加者でした。長靴、バケツ、袋、軍手、雨がっぱ、棒切れ等々、皆さん栗拾い準備万端でした。車で来た家族、電車で来た家族が揃って、栗拾いが始まりました。子供も大人も、体を屈めて、落ち葉に隠れた栗を探し始めました。始めて間もなく、あちこちで「あっ、あった!」「ママ、見て見て!」「こんなに大きい栗見つけたよ。」と歓声があがりました。私が栗のイガをつま先で挟んで割ると、息子がそのイガの中から出てきた栗をつまんで拾い、気がつけば栗が袋いっぱいです。どれだけ栗が拾えたか比べあったり、栗ご飯にしようかマロンクリームを作ろうか等と話しながら、大人も子供も夢中になりました。袋がずっしり重くなりヘトヘトになって、私達家族は拾うのを終わりにしました。重いのもそのはず、家に帰って計ったら4.4キロもありました。
場所を移動し、森の中でピクニックをしました。大人はやれやれと休息する一方で、子供達は次のイベントのドッジボールを今か今かと待っていました。フランスでは「balle au prisonnier」と呼ばれているそうです。浦田校長先生も参加して下さり、男子対女子に分かれ、幼児から大人も入ってゲーム開始。初めてのドッジボールで戸惑う子もいましたが、子供達はすぐにルールを理解していました。味方同士ボールをパスしながら、相手チームを狙うチャンスをうかがうコツを身につけていました。子供たちの目は真剣そのもので、人数あわせに入った私も昔を思い出して、子供達と大いにはしゃいでしまいました。子供たちのキラキラした瞳と可愛い笑顔を間近で見ていると、イベントに参加して良かったと実感しました。浦田校長先生をはじめ、保護者の方々のご尽力によって、子供達の思い出が又一つ増えました。心より感謝申し上げます。
田草川(たそがわ)俊美(ワイルド先生 小3下 土曜クラス)
栗拾いの写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
更新:2014年7月5日
運動会ご報告
6月1日に行なわれた運動会のご報告を
後藤由美様よりいただきました。
2014年運動会感想
6月1日日曜日にAFFJ(日仏家族の会)主催の運動会がIssy-les-MoulineauxにあるParc de l'Ile de saint-Germainで行われ、家族で参加してきました。
毎年行われているこの運動会、今年は過去最高、なんと180人の参加者があったそうです。補習校からは48名が参加しました。
運動会の前々から、当日のプログラム、雨天時の連絡網、グループ分け、そして前もって練習しておけるようにラジオ体操やジェンカの動画がメールで送られてきていたので、我が家では準備もばっちり。当日には既に運動会熱が充分に高まっていました!さすが日本の運動会!
運動会当日。受付ではちまきをもらい、6色の色のチームごとに並び、選手宣誓を聞いたら準備体操。パリの公園で180人によるラジオ体操、圧巻でした。
始めは少し恥ずかしがっていた娘達も司会の方々が楽しく盛り上げてくださったので、種目が始まるころにはすっかり楽しそうにはしゃいでいました。たま運び、障害物競走、かけっこに風船割り競争。。。私はパパ障害物競走のときにマシュマロを持つお手伝いをしたのですが、全速力で突進してくるお父さんたちにタジタジでした。
それぞれのお弁当を見せあって交換しながら食べるお昼ごはん。私の小学校のときもこうだったな、と懐かしく思い出していました。
午後の部はジェンカとアヒルダンスで始まり、綱引き、おんぶ競争、パン食い競争、リレーにたま入れと続きました。パン食い競争のパンがチョコレートパンなのもパリならでは。なかなか取れないパンの周りを口を開けてくるくる回る子供たちや、必死に大きな口をあけてぴょんぴょん跳ねているお母さんたちを見てみんな一緒に大笑い。チーム別リレーの頃には、チームの皆とも仲良くなり、「私のお父さんだよ!」アンカーのたすきをかけて走る父親を大声で応援していました。応援の甲斐なく負けてしまいましたけれど。笑。それでも最後には全員がメダルと参加賞をもらい、皆にこにこでした。
以前学校の宿題に「やかん」という言葉が出てきた時、「やかん」がわからなかった娘にネットの画像検索を見せながら、ちょっと寂しい気持ちになったことがあります。自分にとって当然のことが、フランス生まれの自分の子供には当然ではない。それはこちらに住んでいる日本人の親が誰でも一度は必ず思うことではないでしょうか。運動会、たまいれやパン食い競争も、私にとっては当たり前だった行事ですが、わが子は下手すればマンガやテレビでしか見ることのない日本の一部です。それをパリで子供たちに体験させてあげられて、一緒に楽しく共有できるのは本当にありがたいです。主催の日仏家族会の皆さま、前準備や当日の運行をしてくださった役員の皆さま、そして声をかけてくださった補習校代表の皆さまに心から感謝しております。ありがとうございました。
日本の運動会楽しかったね、来年もまた来たいね、と帰り道に親同士で話す私たち。また来週学校でね!と別れる子供同士を見ながら、なんだか日本の学校みたいで嬉しいな、と思う母なのでした。
後藤由美(新一年水曜クラス)
運動会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
更新:2014年5月5日
かるた会ご報告
4月5日に行なわれた「かるた会」のご報告を
三力谷良子様よりいただきました。
かるた会
風が少し冷たく感じられた快晴の4月5日土曜日に、恒例の「かるた会」が開催されました。
事前の参加人数が少なく、運営に携わった方々が心配していたようですが、例年と変わらぬ参加人数のもと、盛況のうち終えることができました。
当日は校長先生はじめ、授業を終えられた先生方もかけつけて下さり、子供たちに混じってかるたをして頂いたり、保護者たちと談笑される姿がありました。
サンドイッチや手毬寿司、チョコレートケーキやマドレーヌなど保護者たちの手作り料理等々が並べられている中、子供たちは誰かれとなく「かるた」の前に集まり、そこからいくつかの小さなグループに分かれて自然とかるた会が始まりました。読んでいる札の意味をお母さんに聞きに来る子やちょっと難しそうだけど百人一首に挑戦してみようと思っている子、未就学生だけどお兄ちゃんお姉ちゃんを見て、見様見真似で参加している子や百人一首で盛り上がる中高生のグループなど、年齢は違ってもみんなが「かるた」を楽しいと思っている様子が伝わってきて、こちらの気持ちも春の陽気のようにあたたかくなりました。
フランスで、また現地校に通っている場合、同年代の子たちと競って「かるた」をする機会はほとんどないに等しく、また週1回補習校で学んでいる日本語を駆使してこのような会に喜んで参加している姿をみると感慨深いものがありました。息子のクラスのワイルド先生3年下クラスでは、丁度授業で「かるた」を勉強しているところだったので、知識と実践の両面で遊ぶことができ、良い機会だったと思いました。
子供たちは勿論のこと、保護者たちも美味しいお食事とお菓子と共に、学年やクラスを越えての交流に積極的に参加され、和やかな雰囲気のなか今年もかるた会が終了いたしました。外に出ると風の冷たさが頬に心地よく良く感じられました。
最後になりますが、企画、準備、運営に携わった保護者代表や保護者の方々、また当日お手伝い頂いた土曜日セキュリティ担当の奥山さんに感謝いたします。
また、校長先生はじめ先生方、お忙しい中ご参加下さり、ありがとうございました。
三力谷良子(土曜日ワイルド先生小3下クラス)
かるた会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
更新:2014年2月5日
音読発表会ご報告
1月18日に行なわれた音読発表会のご報告を
運営委員の笠井かおり様よりいただきました。
音読から朗読へ − 今年も感動!「音読会」
頬を紅潮させ、教科書を持つ手はまっすぐ、視線は真剣そのもの。
いろんな髪の色、目の色、肌の色をした、十人十色の子供たち。「日本語力」という共通のすばらしい武器の研鑽を重ね、1月18日(土)、ついに「音読会」当日を迎えた。
数年前、はじめて参加したときは、『「音読会」?ただ教科書を読むだけ?何だかつまんなそうだなぁ〜』と心ひそかに思いつつ聞きに行った。そもそも「音読」という言葉、私が子供だった時代にはあまり聞いたことがなかったような?・・・で、調べてみると、
「音読」→ 正しく、はっきり、すらすら読むこと
なるほど。海外に住む日本人子女にとって、母国語である日本語学習の要ともいえるエクササイズなのだな、と理解。
しかして・・・学年が上になるにつれ、次第に「音読」を超越し、読み手の感情が心に伝わる「朗読」の域に入ってゆくではないか。
「朗読」→ 上記プラス、作品の意図、場面の雰囲気、登場人物の性格や 心情を、音声で表現すること (文科省HPより)
すばらしい・・・涙が出てしまいそうだ。来賓も「ブラボー!」、拍手喝采。
普段現地校に通う子供たちにとって、フランスの厳しい学習プログラムと平行して日本語学習を続けることはけっして容易ではない。特に高学年になるにつれて「日本語アレルギー」を発症する割合は高まり、親は何とか日本語を続けてほしい、と頭をひねり、叱ったり、おだてたり、はたまたケンカしてみたり。それを乗り越えて親子でがんばった成果がこの「音読会」ともいえよう。
人前に出るのが恥ずかしくて真っ赤になる小さな子もいる。少しフランスのアクセントが入っている大きな子もいる。でも、本国の学校でもこんなに堂々と発表する子たちにはなかなかお目にかかれまい。指導してくださった先生方のご尽力に頭が下がる。
発表後は、お楽しみの「お茶の会」。ガレットにジュース(大人はシードル)で、カンパイ! 保護者の皆さんにご協力いただき、今年も楽しく幕を閉じた。
保護者代表 笠井かおり
音読発表会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
また「在校生・保護者のみなさんへ」ページの「校長先生のフォトギャラリー」にも掲載しています。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2013年11月5日
秋の遠足 ムドンの森での栗拾い
10月13日、日曜日の朝、青空を見てヤッホーと叫びたくなるくらい嬉しい気持ちになりました。毎日お天気が悪かったせいで、この日のお天気がとても心配されました。でも、良いお天気に恵まれ、太陽の下でのピクニックはポカポカとして、本当に気持ちが良かったです。恒例 のドッジボールも楽しかった!
今回、RERのC線が工事中で、ムドンの森にたどり着くのに4時間もかかってきてくださったご家族もありました。参加してくださったご家族の皆様、どうもありがとうございました。
栗もたくさん拾って、皆さんはどうお料理されましたか?
保護者代表 六藤佳世子
更新:2013年6月10日
運動会ご報告
6月1日に行なわれた運動会のご報告を銅直(どうべた)千晴様よりいただきました。
運動会
6月1日が運動会とのお知らせを頂いてから、降り続く雨空を眺めたり、天気予報で一喜一憂された参加予定のご家族の方も多かったのではないでしょうか。当日は朝より青空が広がり、みんなの祈りが届いたようなお天気となりました。
場 所は新緑の美しいParc de l'lle de Saint- Germain。開会前に受付で頂いた青や緑などのグループごとのはちまきを締め、11時開始。選手宣誓の後、まずはアンパンマン体操、ラジオ体操で体を ほぐしました。運動会を経験したことのない子はびっくりして傍観する様子もありましたが、障害物競争、借り物競争など、子供も親も一緒に参加する競技が進 むにつれ、次は何の競技?とピンク色の頬をした子供たちの楽しむ様子がありました。お腹ペコペコでお昼ご飯を頂いた後、午後の部はまずチアリーダーの持つ ポンポ ンを使ったダンスがあり、リズムの良い曲にノリノリで踊る子供たち。その後幼児、小児、大人と分かれて綱引き、パン食い競争、リレーなどをしました。どの 子も真剣勝負、綱を引く顔が真っ赤になり、歯を食いしばって懸命に走る姿に全員がエールを送りました。大人の部も皆さん手を抜かれると思いきや、闘志満々 でしたね。最後には玉入れやくす玉割りもありました。くす玉は割れると沢山の飴玉が落ちてきて、小さな子供たちは歓喜とともに手一杯に飴をとり、小学生の 子供たちは知恵を働かせTシャツの裾を使ってより多くの飴をとりました。閉会の際にはごあいさつと子供たちにはまたもやプレゼントがあり、シャボン 玉、鉛筆 などを頂きました。そして忘れてはいけないのが金色のメダル !子供たちの笑顔と同じキラキラした全員1等賞のメダルでした。
お誘い頂いたフランス家族会の方をはじめ、グループ分けや沢山の競技の準備して下さった方々、当日にお世話をして下さった方々、この場をかりまして深く御礼申し上げたいと思います。期待以上の運動会、来年もぜひ参加させて頂きたいと思います。
銅直(どうべた)千晴(西岡先生小1上 土曜クラス)
運動会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
更新:2013年5月10日
カルタ会ご報告
4月13日に行なわれたカルタ会のご報告を日疋敬子様よりいただきました。
かるた会
風はまだ冷たくても一雨ごとに春の訪れが感じられた4月13日(土)に恒例のかるた会が教室として使われているSaint Francois d'eylou校の体育館で開催されました。
父兄手作りの巻き寿司やパイやタルトが脇に並び、今年は初の試みで、授業で先生方が使われる教材やコピー代等の足しにとバザーが同時に行なわれました。参加者は内部者に限られましたが、生徒とその親御さんで総勢70名程集まられました。子供達にとっては、普段、授業のある時にだけしか会う機会のないお友達と、学年やクラスを越え交流できる、またとない機会でもあります。広げられた何枚ものピクニックシートに、誰が指示しなくとも、自然と同年代の子供達とグループを作り、各自持ち寄りのかるたを選んで、会スタートです。低学年は大人が札を読みますが、高学年になると札を読むのも子供の役割。和気あいあいと大盛り上がりです。あるグループでは、いつどこで習っているのか百人 一首をトライしていました。標準のかるたとは異なるゲーム式のカード取りをしているところもありました。かるたも父兄が持ち寄っているので、キャラクター物から真面目な物まで多種多様です。
かるた取りといえば、日本で育った者には正月の恒例遊びなので、多かれ少なかれ知っている遊びですが、フランスで生まれ育った多くの子供達にとっては、とても新鮮な遊び、かつ一週間に1度習っている日本語が使える絶好の機会のはずです。またお正月おじいちゃん、おばあちゃんの大人と取るかるたと同年齢の子供のみとでは、一味も二味も楽しさが違うことでしょう。一等賞とかはありません。ただ楽しく何度も遊びます。
クラス担任の先生方も見守ってくださっていました。
我が家の娘は日本生まれですが、2歳半から外地生活、かるた取りはここ補習校で初めて経験しました。
かるたの後はお待ちかね、父兄や先生方と一緒に持ち寄り手料理のバイキングです。参加した父兄が何かしら持ち寄っているので量は十分。ジュースやあたたかい飲み物もあります。娘は巻き寿司を真っ先に、私は抹茶のスポンジケーキやオリーブの入ったスポンジケーキをいただきました。どれも美味!お母様方ご苦労様でした!
個人的に私はバザーを担当しました。衣類や日本語の本、おもちゃにパズル、布、 バックなど、どれも新品かほぼ新品同様なのに、お値段は2ユーロ、3ユーロ、小さいおもちゃは10サンチームで販売です。初の試みでしたが、少ないながらも売り上げができ、先生方の授業材料に貢献できたことは良かったと思います。残念なのは、バザーのためかるたをする場所が少し狭まったこと、出品された方と買われる方の児童の年令差が少ないため、洋服サイズやおもちゃの対象年齢があわなく、在庫がたくさん残ったことでしょうか。試みとしては良かったと思います。
最後にいつもとても楽しい会を企画、実行、協力してくださる、保護者代表をはじめクラス代表の皆さん、そして各父兄の方々に感謝いたします。 校長先生を始め、先生方、お忙しい中参加していただき本当にありがとうございました。
日疋 敬子(ワイルド先生小3上 土曜クラス)
かるた会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
また「在校生・保護者のみなさんへ」ページの「校長先生のフォトギャラリー」にも掲載しています。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2013年2月10日
音読発表会ご報告
1月19日に行なわれた音読発表会のご報告を
運営委員の山本晶子様よりいただきました。
音読発表会ご報告
1月19日に音読発表会が行われました。音読発表会は年に一度行われるパリ日本語補習校の学校行事です。
今回は前夜から降り始めた雪で参加者の遅刻や欠席が心配されたものの、大幅な遅れもなく前半、後半ともに無事に終了しました。
当補習校では、現地校に通うお子さんも多いかと思います。そういったお子さんにとってはこの発表会は沢山の人の前で「日本語で表現する」数少ない機会だと思います。そういったお子さんを見守るご父兄の方々にとっても貴重な機会になるのではないでしょうか。
音読発表会では、低学年から高学年の順で発表していきます。どの子も皆真剣そのものです。その子供達の姿を見守るお父さん、お母さん、そして先生方の表情もまた同じく。。。そしてそれぞれ発表を終わったときのお子さん達のホッとしたお顔がとても微笑ましいです。その表情には、「ああ、終わった。」という安心と、そして「出来たぞ!!」という満足感が混ざっているように思えます。
発表会後にお茶会の時間が設けられました。今回で2回目になるこのお茶会の準備をわたくしは保護者代表の一人として六藤さんとご一緒にさせていただきました。皆様に少しでも楽しいひと時を過ごしていただけたらという思いで、そしてクラス代表の皆さんにも相談をしたりお手伝いをしていただきながら進めました。普段先生と、またご父兄同士でお話をする機会は中々ないと思いますので、このお茶会が皆様の交流の時間になったとしたら光栄です。
音読発表会は今後も是非続けていっていただきたいと思います。
このような貴重な機会を与えてくださった浦田校長先生、各先生方に心より感謝いたします。
山本 晶子
音読発表会の写真を掲載しました。こちらからご覧下さい。
また「在校生・保護者のみなさんへ」ページの「校長先生のフォト
ギャラリー」にも掲載しています。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2012年11月5日
栗拾いご報告
10月14日の栗拾いに参加してくださった皆様へ
先日、雨にもかかわらずたくさんの方に
参加していただきました。
小さいお子さんと一緒に来てくださった方も
数家族あり、雨の中本当に大変だったと思います。
雨のおかげといってはなんですが、
雨の降った後にはたくさんの栗が落ちているらしく、
嬉しくなるくらい一面に栗が落ちていました。
大人も子供のように必死になって拾いましたよね。
今回は栗拾いだけで終わってしまいましたが、
来てくださった方に心より感謝いたします。
ありがとうございました。
この場をお借りしまして来て下さいました
校長先生にも厚くお礼申し上げます。
六藤佳世子
栗拾いのご報告を、新井輝美様よりいただきました。
秋の遠足 栗拾いに参加して
10月14日 日曜日、待ちに待った日本語補習校、秋の栗拾い
数日前からお天気が良くなるようにと
子供と2人お天気を気にしていましたが、
皆様も同じ気持だったと思います。
天気予報が100%当たってしまい 朝から、しとしとと雨
栗拾いは雨でもできる、と雨でも決行という知らせが
あったので 雨が降っても前日から行く気満々でした。
今年我家は3回目の栗拾い、毎年楽しみにしています。
今年の参加家族は6家族と雨にもかかわらず、
集まってくださいました。
栗拾いには毎年、浦田校長先生も参加してくださり
子供達は校長先生とドッチボールをするのが
楽しみの一つで 栗拾い=ドッチボール
今年は雨が止まなかったので 校長先生とドッチボールを
楽しむことができませんでした。残念。。
二時間ほど栗拾いをして、私は4キロぐらい栗を拾いました。
今年の栗は去年より大きい?みなさんどうでした?
森からパワーをもらって雨が降っていたにもかかわらず
いっそう元気をもらい 森の木々が雨にぬれて
キラキラと気持良かったですね〜
自宅に戻り今年はフライパンに穴を開け焼き栗をしました。
15分ぐらい焼くと皮がきれいにむけます。
皆様はどんなお料理になりましたか?
フランス人家庭にどんなふうに栗を利用するか聞いたところ
冬は暖炉で焼き栗 私達のみかんにコタツっていう
感じなのでしょうか?
暖炉で焼き栗 なんだか素敵な感じですよね〜
今回 この秋の栗拾いの準備をしてくださった、六藤さん
ありがとうございました。
校長先生、雨の中、子供達と一緒に楽しく栗を一緒に
拾ってくださってありがとうございます。
水曜日クラス小2下 新井輝美
栗拾いの様子を校長先生が写真に納めて下さいました。
「在校生・保護者のみなさんへ」のページの
「校長先生の補習校フォトギャラリー」からご覧下さい。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2012年7月5日
運動会ご報告
6月10日に行なわれた日仏家族の会主催の運動会のご報告を
渡辺信子様よりいただきました。
運動会
毎年、日仏家族の会が主催される運動会に、今年も日本語補習校の生徒が誘われ、他の家族の方たちと参加させていただきました。
6月10日の日曜日、当日はお天気が心配されるなか 会長挨拶、選手宣誓のあと「雨雲をふきとばせ!」のかけ声とともに11時に開幕されました。まずはラジオ体操。音楽が始まると自然に体が動いていき 、最後の深呼吸で、すがすがしい気持ちになりました。
今年は総勢120名ほどでしたでしょうか。おむつをした2歳の女の子から6年生の男の子まで、家族ごとに六つの色グループに分けられ、年齢にあわせ、障害物競走、借り物競争、綱引き、パンくい競争、リレー、玉入れと懐かしい競技に参加しました。腕立て伏せやなわとびの並ぶ障害物競走に奮闘するお父さん。人形を背負った子供をおんぶしてゴールするお母さん。綱を引く子供にコツを教えながら声援を送るおじいさん。コースの途中から引き返してしまう女の子など、ほほえましい光景がありました。
午前の部が終わると、運動会のもう一つの楽しみでもあるお弁当の時間。芝生に敷物を広げると、隣の家族からお裾分けなどもあり、みんなでわいわい言いながらいただきました。また校長先生もかけつけ子供たちの姿を写真に収めてくださいました。
午後の部の最初の「マルマルモリモリ」でポンポンを手に付け、大人の振り付けを真似て踊る子供たちの真剣な顔。また休憩にだされた冷たいジュースをおいしそうに飲む上気した子供たちの顔。最後のくす玉わりで、落ちてきた色とりどりのあめをあわてて集める子供たちのうれしそうな顔が子供の頃の友達の顔に重なるようでした。
終了時間の15時まであっという間でした。表彰式の代わりに子供たち全員に金メダルとシャボン玉がわたされ、それぞれが帰途につきました。遠くにポニークラブの柵が見え、ここはフランスだった、と我に帰ると空からポツポツと雨粒が・・・。
場所は、パリ15区のJavelからRERで二つ目の広大な緑の敷地をもつセーヌ川に浮かぶイル・サンジェルマン。今年参加を逃してしまった方も来年はぜひ参加してみてください。楽しいこと保障つきです。
渡辺信子
運動会当日の様子を校長先生が写真に納めて下さいました。
「在校生・保護者のみなさんへ」のページの
「校長先生の補習校フォトギャラリー」からご覧下さい。*閲覧には、IDとパスワードが必要です。
更新:2012年6月10日
希望祭ご報告
6月3日にパリ大学都市日本館で行なわれた希望祭のご報告を運営委員の
六藤佳世子様よりいただきました。また当日の会場の様子を校長先生が写真に
納めて下さいました。写真はこちらからご覧下さい。
「希望祭についてのお礼とご報告」
6月3日に行われました希望祭が無事終わりました。
お天気が大変心配されましたが、少しぱらついたぐらいで大雨にもあわず少し肌寒い感じではありましたが、何も問題もなく終了いたしましたこと、嬉しく思っています。
この希望祭につきまして、皆様のご協力、そして今年はSOSママクラブの津田様にお力をお借りし、クラブの方々にもご協力いただきました。本当はお一人おひとりにお礼を申し上げたいところですが、いつもお手伝いいただいてる方々をはじめ、補習校のお母様方の中でも普段お会いしない方や、ママクラブのお顔も知らない方々もあわせ、たくさんの方に助けていただきました。この場で皆さんに同時にお礼をさせていただくこと、お許しください。本当にありがとうございました、心よりお礼申し上げます。特にスタッフとしてお手伝いいただきました方々、本当にご苦労様でした。
今回、去年同様バザーコーナーと食べ物コーナーを設けました。
売り上げ全額金は、693,45ユーロです。このうちから、10パーセントは参加費として日本人会にお支払いし、その残りは日本への義援金として
- 子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク
- あしなが育英会、津波遺児募金
この2つに送られることが、参加者の皆さんの投票で決まっています。きっと日本の方々にとって必要な額からは程遠い金額ではあると思いますが、1人では何も出来なくてもみんなですれば大きな力になり、少しでも助けになると信じています。
皆様、本当にありがとうございました、心から感謝しています。
運営委員 六藤佳世子
更新:2012年4月5日
「カルタ大会」ご報告
3月31日に行なわれた「カルタ大会」のレポートとお写真を
若山和子様よりいただきました。ありがとうございます。
写真はこちらからご覧下さい。
日本語補習校 カルタ会
3月31日(土)午後にカルタ会が開かれました。
4時すぎから、授業が終了した生徒がつぎつぎに集まり始めました。会場にはみなさんがそれぞれ持参して下さったいくつものカルタが集められ、難易度別にビニールシートの上に置かれました。一番初心者には「ちびまるこちゃんのことわざカルタ」「のりものかるた」「へんてこカルタ」。早速一年生のクラスのこどもたちが5人くらい集まって、どれからはじめようか、大騒ぎです。やっとカルタを並べたところで、みんな「読みたい!」。じゃあ、順番で、ということになりましたが、読む子も一生懸命だし、札を取る子も夢中です。大人が読んであげなくても、きちんと子供たちだけで最後まで読み通してひとつのカルタを終え、そしてまたつぎのカルタを始めていました。こどもたちの集中力に感心しました。
その横では男の子たちが集まって3人で夢中になっていて、その向こう側では2年生のクラスの女の子たちが集まって、わいわいと「淡路島カルタ」や「江戸いろはかるた」をしています。こちら和気あいあいとしています。そして一番向こう側には4年生の子供たちが真剣に「部首かるた」をしています。つくりやへんの書かれた札がビニールシートいっぱいに広がっていて、大人でもかなり手応えがありそうなかるたです。こちらは海外子女教育財団の教材予算で、廣重先生が選び購入されていたものだそうです。一番遅くまで授業のあった中学生のクラス、新一年生のクラスのこどもたちも5時ころから参加して、総勢60人くらいが集まりました。保護者のかた、先生方、校長先生も揃い、賑やかで楽しい会となりました。
カルタが、こんなに盛り上がるものだとは知りませんでした。一回くらいやってみたら飽きてしまうものかと思っていたのに、結局おやつの時間までずっと集中してカルタに向かっていたのには驚きました。百人一首に挑戦している中高生の姿もすてきでした。
子供たちがかるたに夢中になっている間に、保護者の方々が協力してすてきなビュッフェを用意してくださいました。みなさんがそれぞれお持ち頂いた、手作りのケーキサレやヒレカツサンドイッチ、かやくごはんのおむすび、手巻き寿司、パイナップルケーキに抹茶ケーキ、キャンディー、飲み物などなどがテーブルいっぱいに並べられ、かるたでお腹をすかせたこどもたちに大人気でした。おやつのあとはまたかるたを始める子供たち、校庭で走り回る子供たち、話に花を咲かせる保護者の方たち、みなそれぞれが楽しい時間を過ごしました。このイベント、また来年も楽しみです。
土曜日 小2下クラス保護者代表 若山和子